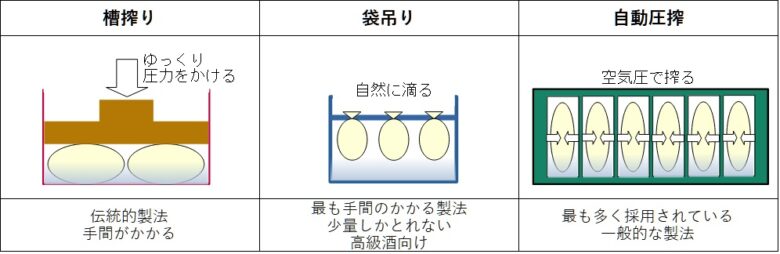文字数:約1100文字
酒瓶によく「山廃仕込み」などと書かれたラベルが貼られている。
これがどのようなものかについて、説明する。
日本酒は酒母の造り方で以下のように分類できる。

●酒母(しゅぼ)とは
酛(もと)とも呼ばれ、アルコール発酵に必要な酵母を増殖させた酒の元のこと。
もろみ造りの際に、最初のアルコール発酵をスムーズ行うために、酒母を使用する。
酒母には主に、乳酸の取得方法で生酛系酒母と速醸系酒母がある。
それ以外にも古典的なものとして、水酛や菩提酛がある。
生産される日本酒の約9割が速醸系である。
●生酛系酒母(きもとけいしゅぼ)
江戸時代に確立された製法で、乳酸を添加せず、天然の乳酸菌から乳酸を得る。
複雑でしっかりした味わいになるのが特徴。
天然の乳酸菌が乳酸をつくる時間がかかるため、酒母完成まで約1カ月かかる。
生酛系酒母は山卸しという作業の有無で、生酛と山廃酛に分かれる。
山卸し(やまおろし)は酛摺り(もとすり)とも呼ばれ、タンクに入れた蒸米をすり潰す作業である。
蒸米をすり潰すことで糖化の進行を早まる効果があるが、手間のかかる重労働である。
- 生酛(きもと)
山卸しを行うため、とても手間がかかる。
しっかりとしたうま味が出る。
酒母造りに約1カ月かかる。 - 山廃酛(やまはいもと)
山卸しを廃止したので略して山廃という。
明治時代に開発された製法。
複雑でコクのある味わいになる。
酒母造りは、生酛と同様に約1カ月かかる。

●速醸酛系酒母(そくじょうもとけいしゅぼ)
明治時代に確立された製法で、醸造用乳酸を添加する。
管理がしやすく、安定した品質が得られ、酒母完成が早い。
生酛系に比べて、淡麗ですっきりした味わいになるのが特徴。
- 速醸酛
最も一般的に使われている製法。
添加した乳酸によりタンク内が酸性になることで、雑菌の繁殖を抑える。
酒母造りは約2週間かかる。 - 超速醸酛
糖化を早めるために、蒸米を使用せず、米麹とお湯のみで仕込む。
酒母造りを約3日で終える。 - 高温糖化酛
始めの仕込み温度を高く設定し、雑菌の増殖を抑える。
酒母造りは約8日間かかる。
●あとがき
速醸酛の新しい手法が開発されるのとは逆に、古典的な菩提酛を実践してみたりと、
これまでにないものを造ろうとする新しい時代が来ていると感じる。
日本酒の造り方はホントにさまざまであり、これによって多様な製品が造れる。
日本酒を飲むときに、造り方を知って飲むのと、知らずに飲むのでは感じ方も変わってくる気がする。