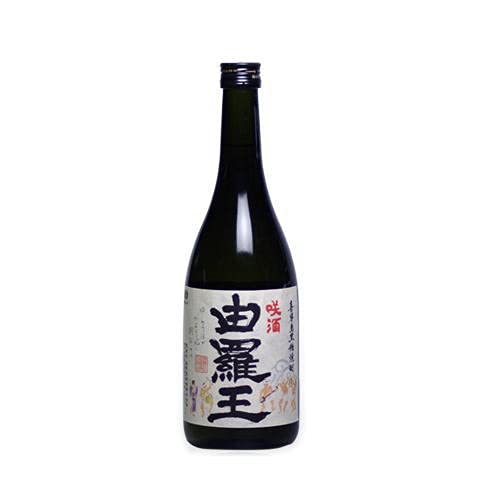文字数:約1000文字
焼酎に使われる原料はさまざまである。
使ってはいけない原料はあるが、それ以外はなんでも使ってよい。
使わなければならない原料の指定がないのが、他のお酒と大きく違う点である。

●黒糖焼酎
黒糖焼酎は黒糖を原料とし、奄美群島のみで造られている。
奄美群島は奄美大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島の五島である。
黒糖の風味とコク、すっきりした甘さがあるのが特徴。
・黒糖について
焼酎の定義として、含糖物質を使ってはいけないことになっている。
含糖物質とは、砂糖や蜂蜜、メープルシロップなどの糖を含むもの、
つまり黒糖も含糖物質となる。
使用禁止の理由は、すでに糖を含んでいるので、
糖化の作業が不要になってしまうためである。
黒糖焼酎は特例とされている(詳細下記)。

黒糖はサトウキビの搾り汁を煮詰めて作られるが、
同様にサトウキビから造られる蒸留酒としてラム酒がある。
黒糖焼酎はラム酒と区別するため、米麹を使用しなければならない。
沖縄県産や外国産のサトウキビが使われることが多い。
外国産は安く、また沖縄産も特措法の補助金があるため安い。
奄美産はこれらよりも高く、また黒糖製品や菓子用に使われて、
焼酎用には回ってきにくい。
関連記事 ↓


●黒糖焼酎の歴史

江戸時代に奄美へサトウキビが伝わったとされる。
それ以前には米や麦、芋、ソテツ、粟などで焼酎を造っていた。
サトウキビを製糖し、黒糖から焼酎を造るようになるが、
薩摩藩によって黒糖による焼酎造りが禁止される。
黒糖は献上品として扱われ、貴重な品となったためである。
太平洋戦争後の米軍統治下で、食糧不足が続き、
米を使わないことを条件に自家用の酒造りが認められ、黒糖を原料にした。
昭和28年(1953)に奄美群島が本土復帰となる。
これに伴い、日本の酒税法が適用になるが、
含糖物質を原料に使用するものは「スピリッツ類」の扱いとなる。
当時の税率は焼酎よりもスピリッツのほうが5割ほど高い。
奄美の酒造組合が政府に陳情することで、
「米麹の使用」、「奄美群島区内での製造」を条件に特例が認められた。
もともと奄美では焼酎や泡盛を造る際に米麹を使用していたため、
何も問題はなかった。
●あとがき
奄美でしか造られていないという特別感、中小規模での製造による希少性が、
黒糖焼酎の魅力を高めている。
ラム酒に比べて度数が低いことや、税率が低いことなどから、手に取りやすい。
米麹を使っているので、ライトな口当たりになり、飲みやすいのも好まれる要因だろう。
ラム酒ばかり飲んでいて、たまに黒糖焼酎を飲むとホッとする。