文字数:約1100文字
ジンは他のお酒に比べて、日本での定番商品がはっきりしている。
これまで、あまり種類がなかったことが要因だろう。
現在はクラフトジンも増えたが、ジントニックやマティーニなどの
クラシックカクテルには定番のジンが使われる。
味、品質、流通が安定していることが重要である。
バーなどに常備されているジンを見てみよう。
●基本情報

- 商品名:ビーフィーター ロンドン ドライジン
- 英 字:BEEFEATER LONDON DRY GIN
- 生産地:イングランド
- 創業年:1820年
- 創業者:ジェームス・バロー
- 現所有社:ペルノ・リカール社
- 日本取扱:サントリースピリッツ(株)
●ボタニカル
ビーフィーターのボタニカルは、以下の9種である。
- ジュニパーベリー
- コリアンダーシード
- アンジェリカシード
- アンジェリカルート
- オリスルート
- リコリス
- アーモンド
- レモンピール
- セビルオレンジピール
薬剤師であったジェームス・バローが選び抜いた材料である。
シトラス系(レモンやオレンジ)の材料を初めて取り入れたのが、
ビーフィーターだと言われている。

スペイン セビリアのオレンジは、バローが知り合いの貿易商から入手していた。
現在も伝統を守り、セビルオレンジが使われ続けている。
これらのボタニカルは、蒸留液に24時間も浸漬され、成分抽出が行われる。
長時間かけて抽出されたものを再蒸留して、中心部(ハート)のみを取り出す。
蒸留の始めと終わりの部分をカットすることで、雑味のない安定した味わいが得られる。
●名前の由来
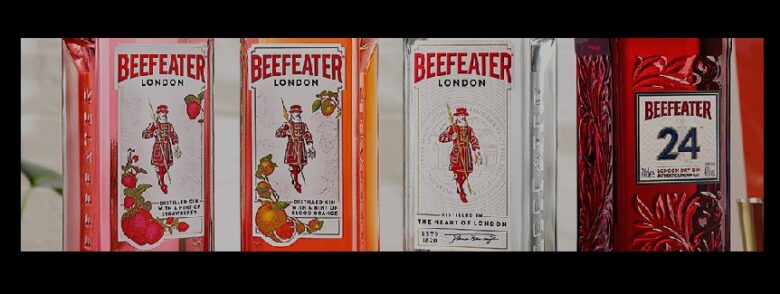
ビーフィーターの名前の由来は、「ビーフイーター(Beef Eater)」である。
ビーフイーターとは直訳して牛肉喰いのことである。
ラベルに描かれているのは、ロンドン塔を守る衛兵であり、
ヨーマン・ウォーダーズと呼ばれている。
この衛兵は、王室主催のパーティーで残った牛肉を持ち帰ることが許されていた。
当時は貴重だった牛肉を食べれることをうらやましがられ、ビーフイーターと呼ばれた。
ロンドン塔を守り続ける衛兵に、自社のジンも守り続けてもらおうということで、
商品名をビーフイーターとしたのである。
●あとがき
牛喰い(Beef Eater)という名前を付けたり、それまでなじみのなかったシトラスを使ったり、
ジェームス・バローはとてもユニークな人だったのだろう。
需要の増加に伴い、製造拠点を移し、ビーフィーターをどんどん大きくしていった。
いまだにロンドンでジンの製造を続けている大手はビーフィーターくらいである。
ビーフィーターは衛兵に守られ続けるのだろう。






















