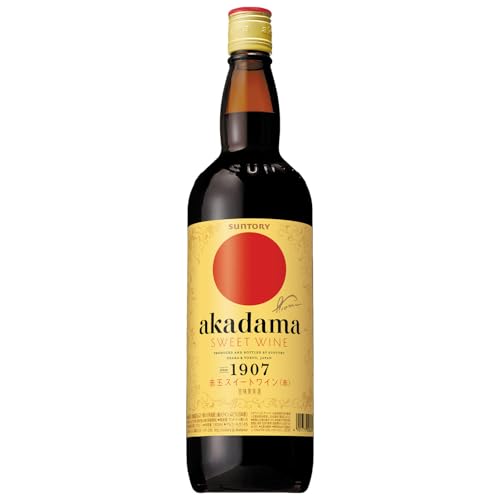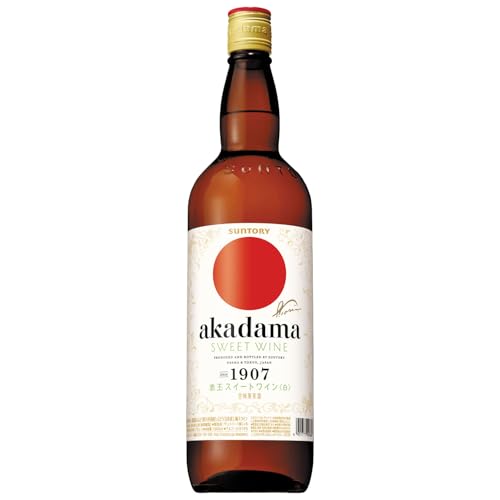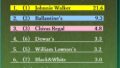●四月の記念日
4月は年度始めであり、出会いの季節である。
新しいお酒との出会いがあるかもしれない9つを紹介。
- 4月1日 :サントリー赤玉の日
- 4月1日 :黒ラベルの日
- 4月1日 :ジャパニーズウイスキーの日
- 4月1日 :居酒屋乾杯の日
- 4月3日 :輸入洋酒の日
- 4月4日 :国際酒ソムリエの日
- 4月10日:酒盗の日
- 4月23日:クラフトビールの日
- 4月28日:ドイツワインの日
・4月1日は『サントリー赤玉の日』
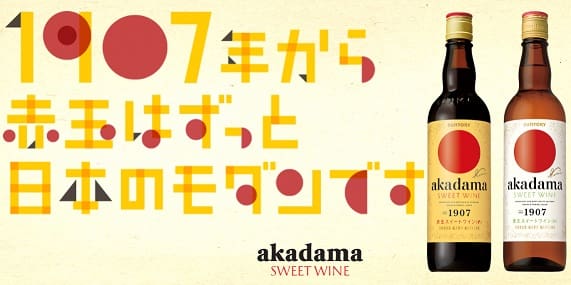
「赤玉スイートワイン」を販売するサントリー(株)が2017年に制定。
サントリーの酒造りの原点である「赤玉ポートワイン」の発売110周年を記念して、
その魅力をさらに多くの人に知ってもらうのが目的。
日付は「赤玉ポートワイン」が発売された1907年4月1日にちなんで。
・4月1日は『黒ラベルの日』

「黒ラベル」を販売するサッポロビール(株)が2018年に制定。
「黒ラベル」は1977年4月1日に発売された「サッポロびん生」の愛称。
その名付け親であるファンへの感謝の気持ちと、
1989年に正式なブランド名となった「黒ラベル」は
今後も愛されるブランドであり続けるとの同社の決意が込められている。
日付は「黒ラベル」の原点である「サッポロびん生」の発売日から。
・4月1日は『ジャパニーズウイスキーの日』

ジャパニーズウイスキーの日実行委員会が2021年に制定。
その歴史や製造方法、他の国のウイスキーとの違い、味わいの特徴などを
幅広く知ってもらうとともに、世界中で高い評価を受けている
ジャパニーズウイスキーをより多くの人に飲んでもらうのが目的。
ジャパニーズウイスキーの礎を築いた先人の偉業を讃え、
生産者を応援する思いも込められている。
日付は1929年4月1日に、
日本初の本格国産ウイスキー「サントリーウヰスキー(通称“白札”)」
が発売されたことから。
・4月1日は『居酒屋で乾杯の日』

居酒屋から日本を元気にしたいとの想いから、
エントリーされた居酒屋の中で日本一の店舗を決める全国大会
「居酒屋甲子園」を運営するNPO法人 居酒屋甲子園が制定。
日本独自の居酒屋文化の継承と業界の発展、乾杯文化を後世に伝えていくことが目的。
日付は「良い居酒屋」「良い乾杯」の「良(4)い(1)」と「酔(4)い(1)」の語呂合わせに、
年度の始まりで飲み会も多く、乾杯をする機会も増えるので4月1日に。
・4月3日は『輸入洋酒の日』
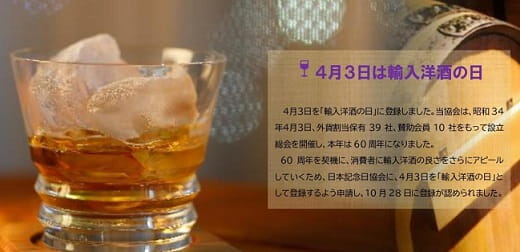
輸入酒類の普及及び宣伝、海外及び国内事業の調査など、
輸入酒類に関しての様々な活動を行う日本洋酒輸入協会が制定。
輸入酒類の専門業者として消費者、同業者に対してその存在感を高め、
輸入洋酒の良さをさらに多くの人に知ってもらうのが目的。
日付は、協会発足が1959年4月3日であることから。
・4月4日は『国際酒ソムリエの日』

ロンドンに本部を置く酒ソムリエ協会(Sake Sommelier Association)が2025年に制定。
この協会は国内外で日本酒の教育・普及促進に尽力している団体である。
日本が桜に彩られる美しい季節に、
長い歴史を持つ日本酒を世界へ広めるために尽力してきた人と、
その努力にスポットライトを当てることが目的。
・4月10日は『酒盗の日』
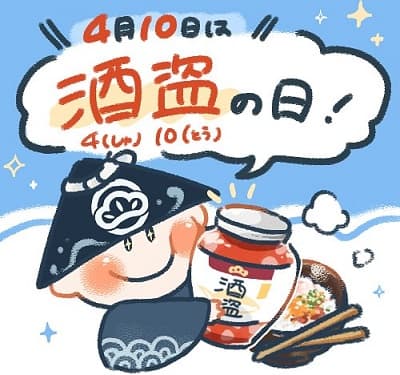
酒盗の製造販売を手掛ける神奈川の(株)しいの食品が制定。
酒盗はカツオの胃腸やマグロの胃を長期熟成させて作る塩辛。
「酒を盗んででも飲みたくなる」というほどにお酒がすすむことから、
その名前がついたとされる。
日本で古くから親しまれてきた発酵食品の伝統の味を今に伝えたいとの願いが込められている。
日付は4と10で「4(しゅ)10(とう)」の語呂合わせから。
・4月23日は『クラフトビールの日』
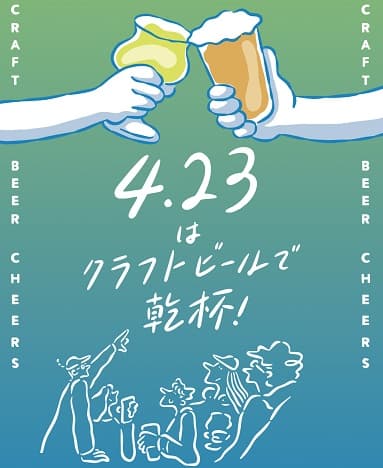
全国地ビール醸造者協議会、日本地ビール協会、
日本ビアジャーナリスト協会などで構成された
日本クラフトビール業界団体連絡協議会が制定。
クラフトビールの普及、ビール文化の向上発展に寄与し、
ビールの愛飲家、製造者、販売者、原料・機器生産者など、
生産から消費に関わるすべての人が一体となる環境を生み出すのが目的。
日付はビールとは一体何かを世界で最初に定めた法律とされる
ドイツの「ビール純粋令」が施行された1516年4月23日から。
・4月28日は『ドイツワインの日』

一般社団法人 日本ドイツワイン協会連合会が制定。
同連合会は各ドイツワイン協会の連携機関で、
日頃からドイツワイン愛好家の育成と愛好団体の支援、
ドイツワインの普及啓発、ドイツ文化の発展への寄与などの活動を行っており、ド
イツワインとドイツワイン愛好家の普及が目的。
日付はゴールデンウィーク(GW)をジャーマンウィーク(GW)にかけて
「ゴールデンウィークにはドイツワインを飲もう」というアイデアから4月28日に。
●五月の記念日
5月は大型連休があり、新緑の過ごしやすい季節。
お酒に関する記念日も多く、6つ紹介しよう。
- 5月5日 :端午の節句
- 5月9、10日:奄美黒糖焼酎の日
- 5月13日:カクテルの日
- 5月第三土曜日:ワールドウイスキーデー
- 5月22日:パロマの日
- 5月29日:胡麻祥酎の日
・5月5日は『端午の節句』
日本の年中行事 五節句の一つである端午(たんご)の節句。
菖蒲の節句とも呼ばれ、薬草である菖蒲を軒先に吊るし、
菖蒲湯に入ることで無病息災を祈りる。
現在では男子の立身出世を願う行事になっている。
菖蒲を刻んで酒に浸した菖蒲酒(しょうぶざけ、あやめざけ)は、
邪気払い、厄除けなどの効果があると信じられてきた。
・5月9、10日は『奄美黒糖焼酎の日』

奄美大島酒造組合が2007年(平成19年)に制定。
奄美の伝統文化継承、風土への感謝、自然環境保護、地域活性、
奄美黒糖焼酎の発展を目的とする。
日付は5・9・10で「こくとう」の語呂合わせから。
・5月13日は『カクテルの日』

1806年にアメリカの雑誌でカクテルが定義が作られた。
1806年5月、米タブロイド紙『バランス・アンド・コロンビア・リポジトリ』において
「カクテル」という名称が初めて登場し、その翌週の5月13日号に、
読者からの問い合わせに対して「カクテルの定義」が初めて文章化された。
このことにちなんで世界的に5月13日は『カクテルの日』とされている。
雑誌の記述では、以下のようにカクテルを定義している。
「蒸留酒に砂糖、水、ビターズ(薬草・香草などで苦みをつけた酒)を加えて作る刺激的な酒」
・5月第三土曜日は『ワールドウイスキーデー』

2012年、当時スコットランドの大学生であったブレア・ボウマンが制定。
SNSで「#WordWhiskyDay」と付けて、
「ウイスキーを楽しもう!」との発信から世界中に広まった。
元はウイスキー評論家として有名なマイケル・ジャクソン氏の
誕生日を記念した「International Whisky Day」と同じ3月27日だったが、
翌年から5月の第三土曜日に変更された。
世界中でウイスキーを自由に楽しむことが目的だが、
まだ日本ではあまり浸透していない。
・5月22日は『パロマの日』
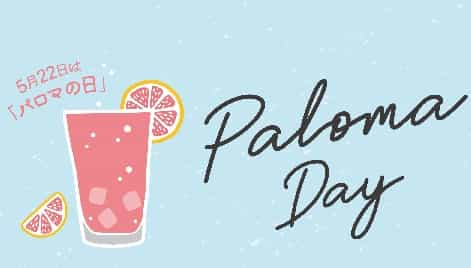
アメリカで制定された「World Paloma Day」が日本でも2021年に制定された。
パロマはテキーラとグレープフルーツジュースを使ったカクテル。
テキーラの本場メキシコでは人気No.1ともいわれている。
テキーラをメスカルに変えるアレンジもある。
・5月29日は『胡麻祥酎の日』

胡麻祥酎ブランドを持つ福岡の(株)紅乙女酒造が制定。
胡麻祥酎の魅力を多くの人に知ってもらうことが目的。
「焼酎」ではなく「祥酎」なのは、
「祥」がおめでたい意味を持つためであり、
慶びにあふれた「口福の酒」として世に送り出している。
日付は5と29で「口(5)福(29)」と読む語呂合わせから。
●六月の記念日
6月は梅雨の季節だが、雨が降ってもお酒は変わらず美味しい。
記念日を8つ紹介するので、天気が悪くてもお酒を楽しもう。
- 6月2日 :イタリアワインの日
- 6月第二土曜日:ジンの日(Word Gin Day)
- 6月11日:梅酒の日
- 6月14日:バーボンの日
- 6月21日:スパークリング日本酒の日
- 6月21日:酒風呂の日
- 6月25日:生酒の日
- 6月30日:酒酵母の日
・6月2日は『イタリアワインの日』

イタリア大使館とイタリア貿易振興会が2007年に制定。
美味しいイタリアワインの認知度を高め、
そのニーズを掘り起こすことが目的。
日付は、第二次大戦後にそれまでの王政が廃止され、
イタリア共和国が成立した1946年6月2日から。
・6月第二土曜日は『ジンの日(Word Gin Day)』

2009年にイギリスののジン愛好家、
ニール・ヒューストンと、エマ・ストークスによって制定された。
元々両氏と友人らが家やバーで個人的に祝うために記念日だったが、
ロンドンをはじめとする都市でイベントを重ねるうちに、世界中に広まった。
・6月11日は『梅酒の日』

梅酒のトップメーカーであるチョーヤ梅酒(株)が2004年に制定。
高品質な梅酒の美味しさを多くの人に味わってもらうことが目的。
日付は日本古来の暦『雑節(ざっせつ)』で、入梅の日であること、
また、青梅の収穫がピークを迎え、梅酒作りに最適な時期であることから。
関連記事 ↓

・6月14日は『バーボンの日』

アメリカでバーボンが誕生した日として「National Bourbon Day」が制定。
1789年6月14日にエラジャ・クレイグ牧師が初めてバーボンを製造した。
アメリカでは毎年さまざまなイベントが開催され、
大量のバーボンが飲まれている。
・6月21日は『スパークリング日本酒の日』

「澪(みお)」ブランドを製造販売する京都の宝酒造(株)が制定。
スパークリング日本酒市場の活性化と、ブランドの浸透が目的。
日付は、「澪」が発売された2011年6月21日から。
・6月21日は『酒風呂の日』
酒風呂の日は3月20日、6月21日、9月23日、12月22日である。
上記3月20日参照。
・6月25日は『生酒の日』

京都の月桂冠(株)が制定。
蔵元でしか味わうことができなかった搾りたての生酒を、
全国どこでも飲めるようにした歴史を伝え、
生酒の魅力を多くの人に知ってもらうことが目的。
日付は、本格的な生酒が発売された1984年6月25日から。
・6月30日は『酒酵母の日』

岐阜の(有)渡辺酒造店が制定。
清酒業界全体で美味しい酒造りに欠かせない酒酵母に感謝し、
来期も美味しいお酒が出来ることを願う日とするのが目的。
日付は、酒造年度の最終日の6月30日から。