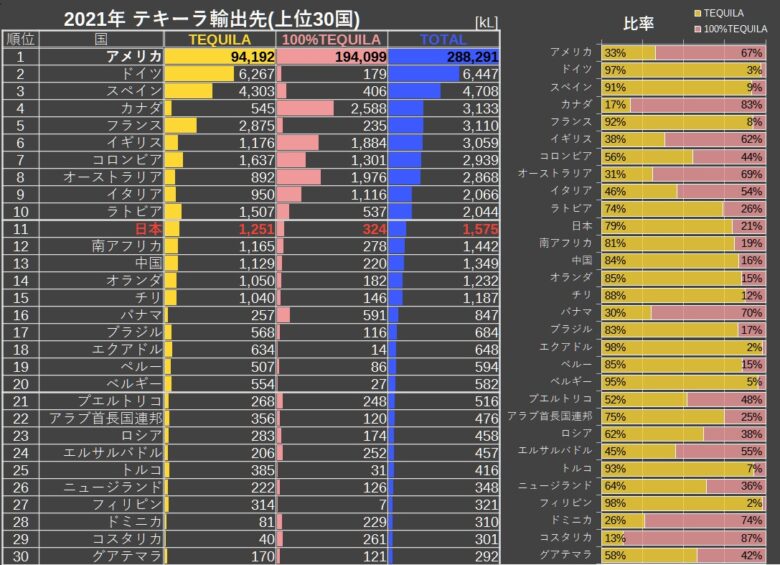文字数:約1300文字
テキーラ人気が世界的に高まっていると言われる昨今、生産量はどうなっているのか。
また、世界的なパンデミックの影響はあるのか、データから見てみよう。
●テキーラの生産量推移
テキーラ規制委員会(CRT)がテキーラの生産量を公表している。
100%アガベテキーラと、(ミクスト)テキーラのデータをグラフにした。
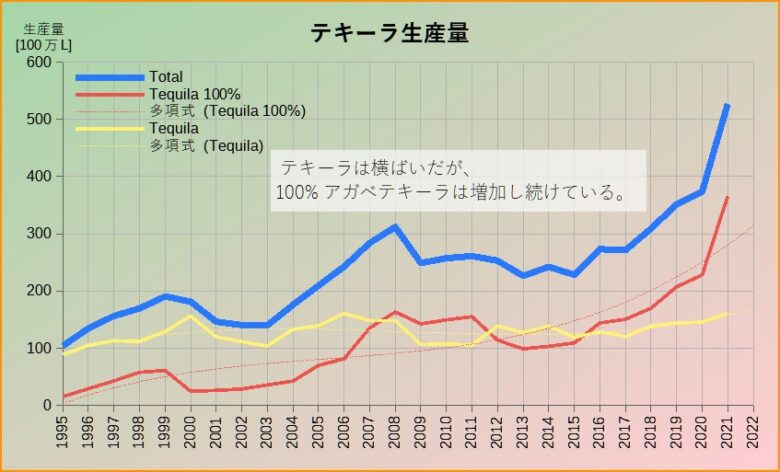
まず、100%アガベテキーラと(ミクスト)テキーラを合わせた生産量は、
右肩上がりに伸び続けている。
個別で見ると、100%アガベテキーラは右肩上がりだが、
(ミクスト)テキーラは横ばいである。
つまり、総生産量が右肩上がりなのは、100%アガベテキーラの生産量が
増加し続けていることに起因する。
世界的な需要は100%アガベテキーラに向けられている。
データを見る限り、テキーラの生産量にパンデミックの影響は無い、むしろ増加している。
世界的に外食が控えられる状況の中でも、テキーラの勢いは衰えない。
今後どこまで伸び続けるのだろうか。
●アガベの収穫量
テキーラ規制委員会はアガベの収穫量を公表していない。
しかし、国際連合食糧農業機関(FAO)がアガベの収穫量を公表している。
ただし、200種類以上あるアガベ種をまとめたものになっている。
メキシコでは、メスカル用や醸造酒のプルケ用、アガベシロップ用、観賞用などの
アガベがあるが、テキーラ用がもっとも多いので傾向を見るには十分である。
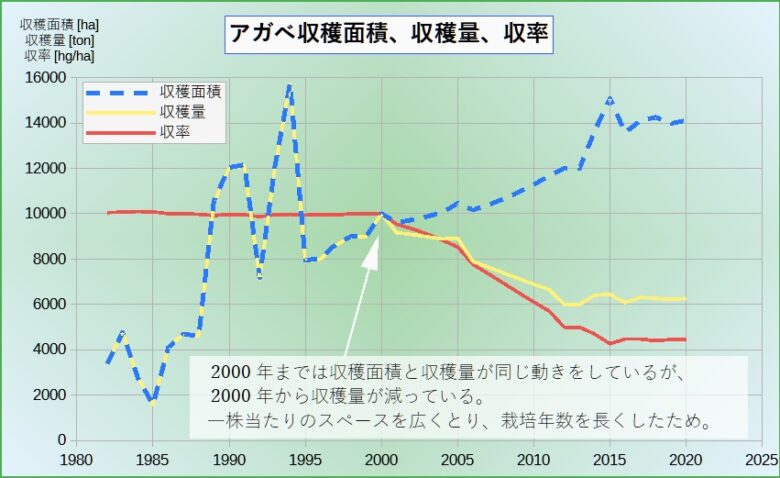
収穫面積と収穫量が2000年まではほぼ一致した動きをしている。
収穫面積が増えると収穫量も増え、収穫面積が減ると収穫量も減るということである。
しかし2000年以降は、収穫面積が増えても収穫量は増えていない。
収率(面積当たりの収穫量)を見ると、2000年までの5割弱で安定している。
収穫面積を増やしたが、収穫量は増えていない。
これは一株当たりのスペースを広くとり、栽培年数を長くしていると考える。
よりプレミアム化を目指しているのだろう。
・世界のアガベ収穫量
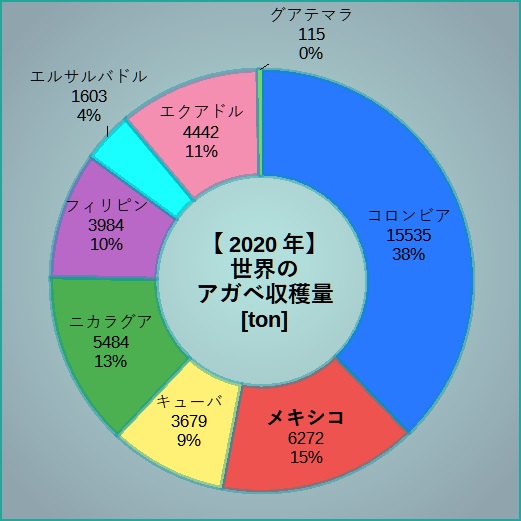
テキーラ用のアガベはメキシコでしか栽培されていないが、
他のアガベ種はメキシコ以外でも栽培されている。
多肉植物なので、観賞用だったり、アガベシロップ用だったり用途は色々である。
テキーラを生産するメキシコが1位かと思ったが、
意外にもコロンビアが倍以上の差をつけている。
観賞用は小さなアガベでもいい値段で取引される(テキーラより高いかも、、、)。
他はキューバ、ニカラグア、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラなど、
やはりメキシコより南の中南米各国でよく栽培されている。
中南米以外では唯一アジアでフィリピンがアガベの収穫データがある。
こちらもやはり観賞用のようだ。
しかしフィリピンは世界有数の蒸留酒大国であり、
ジン、ブランデー、ラムなどを大量に生産している。
もしかしたら今後アガベスピリッツを造ってたりするのだろうか?
●あとがき
データからテキーラ需要の強さを見えた。
しっかりとした管理がされていて、高品質のものが増えて、良い状況が整っている。
原産地呼称制度もあり、ブランド化、プレミアム化が進んでいる。
まだまだこれからも楽しみなお酒である。